
こんにちは。
自己紹介でも少し触れましたが、私の真ん中の子は難病である「痙攣重積型急性脳症」と診断されています。
本記事では、私たち家族の実体験をもとに、
主に、
痙攣重積型急性脳症の概要、
痙攣重積型急性脳症の発症時の様子、
痙攣重積型急性脳症の後遺症、
について紹介したいと思います。
痙攣重積型急性脳症の概要
痙攣重積型急性脳症とは突発性発疹やインフルエンザなどの感染症を契機に、
けいれんと脳の障害を起こす日本で見つかった病気です。
患者数は数千人で、
1年あたりに新たに100~200人が発症すると推定されています。
痙攣重積型急性脳症は日本の小児に特有の病気であり、
生後6か月から1歳前後での発症が最多です。
また、痙攣重積型急性脳症の原因はよくわかっておらず、
難病に指定(指定番号129)されています。
痙攣重積型急性脳症の発症時の様子
私たちの子どもの場合、
発症時は高熱が39℃ほどの10時間ほど続いた後、
急に全身が硬直したような痙攣が発生し、
急いで救急病院へ車で向かったのですが、
また、救急病院でも同じような痙攣が生じてしまったため、
その場で入院がきまりました。
痙攣重積型急性脳症の発症から現在に至るまで
入院してからも、
痙攣重積型急性脳症と診断されたわけではなく(この病気を知らない医師が多いことも事実です)、
発熱に対する治療、
痙攣に対する治療が主な治療でした。
しかし、入院し数日が経っても症状は改善せず、
その病院の主治医も「対処療法しかない」とのことでした。
私たちはだんだんとその治療内容に疑問を持つようになり、
自分たちで子ども専門の総合病院を探し、
そこに転院をすることにしました。
その病院でCTやMRI検査をおこなってもらい(最初に入院した病院はそのような検査も全く行いませんでした)、
痙攣重積型急性脳症の診断が下りました。
転院先の主治医からは、「早く転院してもらってよかった」(痙攣の治療を行い続けると予後が悪くなっていた)、
といわれ、本当に無理をしても転院してよかったと思いました。
そこからは神経科の専門医が治療を行ってくださり、
1か月くらいで退院することができるまでに回復しました。
しかし、発症前までできていた、発語、運動(階段を上る)、笑うことなどは
ほぼできなくなってしまいました。
その状態を放置することは私たちには考えられなかったので、
主治医と相談のうえ、
児童発達支援という制度を利用し、
リハビリを少しづつ行うことにしました。
3歳から6歳まで保育園利用後に18時頃まで月23日、日曜日を除く毎日、
児童発達支援のプログラムを行うこととなりました。
時にはかんしゃくを起こしたり、「行きたくない!」と大暴れした日もありましたが、
基本的に楽しんで児童発達支援にも保育園にも行ってくれました。
でも本人にとっては大変だったかもしれません。
私たちも何が正解だったのか今も考えることがあります。
ただ、事実として、無事に保育園を卒園し、
特別支援学級ではありますが、地域の小学校に通うことができています。
また、病院は半年に1回定期通院をしています(小学校に入ってからは、脳の症状は落ち着いているため、近くの大学病院の精神科に転院となりました)。
痙攣重積型急性脳症の後遺症
現在は知的障がい(療育手帳3度 B判定)と睡眠障害の後遺症が主に残り、
脳波においても「棘波」といわれる波が出ており(てんかんの小発作が常にでている状態)、
お薬を飲みながら経過観察しています。
今小学1年生ですが、
発語は幼児語で不明瞭な単語も多く(精神年齢は3歳前後)、
大人がなかなか本人の言いたいことの全てをくみ取ることができません。
また、自閉スペクトラム症も併発しているため、
気持ちの感情が上手くできず、
家で暴れまくったり、叫んだり、びっくりするほどの大声で泣いたりすることが、
1日に何回も起きます。
そして、服を着させる順番や座る場所などのこだわりも非常に強いです。
両手で何かをすることも難しく、鉄棒やペットボトルのふたを開けるなどのことはできません。
うんちはまだオムツでしています。
発語については言語聴覚療法、
手を使うことは作業療法で
今現在もリハビリを行っています。
児童発達支援は小学校入学前までに利用できる制度なので、
お兄ちゃんが通っている放課後等デイサービスに移り、
学校終了後から18時頃まで一緒に
通っています。
最後に
症例が少ないので、私たちも将来に対する不安もたくさんありますが、
本人も精一杯頑張ってくれているので、
それに寄り添っていこうと思っています。
科学が発達し、治療法が見つかってくれるといいなぁと思いながら毎日を過ごしています。
この子のおかげで私たちも色々なことに気づき、様々な制度についても知れることができました。
またこの子のような困った子どものために自分で児童発達支援や放課後等デイサービスを自分で運営したいという気持ちにもさせてくれました。
児童発達支援や放課後等デイサービス、言語聴覚療法や作業療法については、
別の記事で紹介したいと思っています。
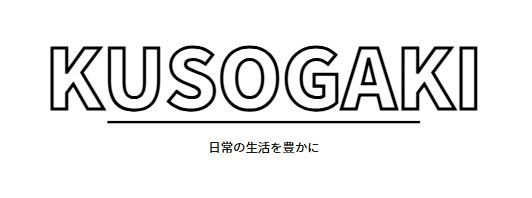



コメント